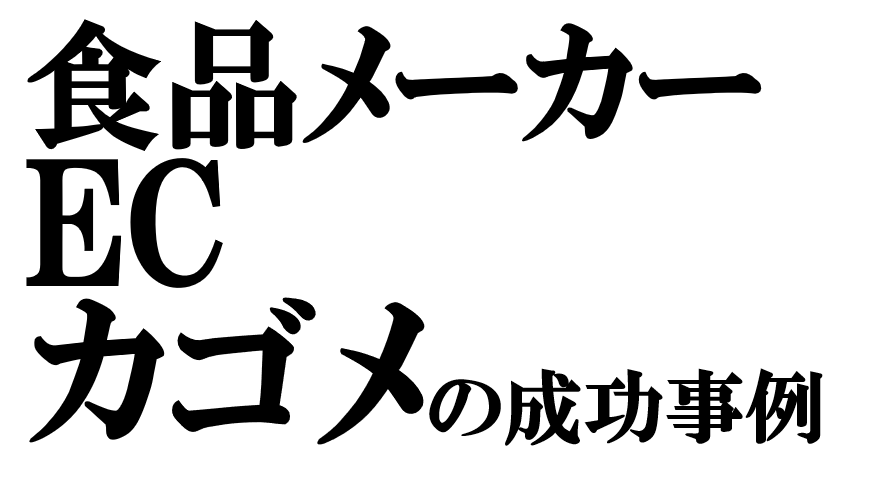
食品メーカーにとって、食品スーパーやコンビニエンスストア、ドラッグストアなどのチェーンストアでの販売は、依然として売上の中心を占めています。こうした小売店舗での売上は大きく、今後もマスマーケティングとしての重要性は変わらないでしょう。
一方、近年は自社ECサイトでの販売を強化し、小売チャネルを補完している食品メーカーも目立ち始めています。
本稿では、まず食品メーカーが自社ECに取り組むメリット・デメリットを整理し、その上で、国内大手食品メーカーであるカゴメのEC戦略を解説します。
メーカーから見た流通チャネル
メーカーが自社で製造した商品を消費者に届けるまでの経路を「流通チャネル」といいます。メーカーから見たとき、商品をどのような経路で流通させるかは、販売戦略の中でも特に重要な要素です。
流通チャネルは、メーカーと消費者のあいだに入る流通業者(卸売業者・小売業者など)の数により、下図のように、「3段階チャネル」「2段階チャネル」「1段階チャネル」「0段階チャネル」に分類され、流通業者が多いほど「チャネルが長い」と表現します。
◆流通チャネルの分類
-鈴木雄高.jpg)
出所:筆者作成。
冒頭で触れたチェーンストアでの販売は、流通業者を介した販売にあたります。具体的には、3段階、2段階、1段階のチャネルで展開されているケースです。
食品メーカーの場合、図中の「小売業」には、イオンやイトーヨーカドーのような総合スーパー、ライフやヤオコー、オーケーなどの食品スーパー、セブンイレブンなどのコンビニエンスストア、ウエルシアやツルハ、コスモスといったドラッグストア、ドン・キホーテやトライアルのようなディスカウントストアなど、多種多様なチェーンストアのほか、小規模な小売業者やECモールも含まれます。
本稿ではメーカーの自社EC戦略について解説します。その前に、流通チャネルにおいて消費者との間に流通業者を置くメリットとデメリットを整理しておきましょう。
メーカーが流通業者を介して販売することの4つのメリット
メーカーにとって、流通業者を経由して商品を販売することによるメリットには以下のものがあります。
メリット1. 広範囲に商品を届けやすい
流通業者の物流ネットワークや販売網を活用することで、全国や複数の地域に効率的に商品を供給できます。自社だけでは難しい遠隔地や多店舗への供給も、流通業者を介することで実現可能です。
メリット2. 需要創出や販売活動を代行してもらえる
流通業者はプロモーションや店頭販促、イベント企画などを行います。そのため、メーカー自身がすべての販売活動を行わなくても、商品認知や購買促進が可能です。
メリット3. 在庫管理や物流の負担を軽減できる
商品の保管、配送、発注調整などを流通業者に任せることで、メーカーの業務負荷を軽減できます。在庫過不足によるリスクも、流通業者が管理することである程度分散されます。
メリット4. 販売リスクの一部を分散できる
流通業者が販売状況や在庫管理を担うことで、メーカー単独で抱えるリスクを軽減できます。例えば、売れ残りや在庫過多のリスクがメーカーだけに集中することを防げます。
メーカーが流通業者を介して販売することの4つのデメリット
一方で、メーカーには、消費者との間に流通業者が介在し、チャネルが長くなることによるデメリットもあります。
デメリット1. 流通マージンが発生し、利益率が下がる
流通業者が増えるほど、取引条件や手数料、販売促進費などのマージンが積み重なります。その結果、商品1単位あたりで得られる利益が減少し、価格政策の自由度も下がります。
デメリット2.消費者の購買行動や意識を直接把握しにくい
消費者の購買実態、主要顧客の属性などを知ることは容易ではありません。同様に、購買理由、使用実態、商品への不満などの情報を取得することも難しいです。これにより、販売戦略、商品開発、マーケティング施策に必要な知見やインサイトを得づらくなります。
デメリット3.小売店頭には競合が多く、伝えたい情報を十分に伝えられない
店頭には他社ブランドが多数並び、パッケージやPOPで伝えられる情報量には限界があります。特に商品説明が重要となる新ブランドや新商品では、消費者に十分な理解や魅力を伝えることが難しいという課題があります。
デメリット4.新商品は小売店に必ずしも採用されず、販売機会が制約される
小売店の棚スペースは限られており、売れる確率が高い既存ブランドの販売が優先されます。そのため、メーカーが時間とコストをかけて開発した新商品でも、店頭に並ばないことがあります。また、発売直後の売れ行きが芳しくない場合、早期に棚落ちする(店舗での販売が終了する)こともあります。販売機会が制約されることは、メーカーの商品戦略において大きなデメリットです。
メーカーが自社ECに取り組む意義と注意点
メーカーの立場から見ると、流通業者を介した販売には大きなメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。 そのため、近年は流通業者を介さない「自社EC」での販売に取り組むメーカーが目立ち始めています。
自社ECサイトでの販売によって得られる4つの効果
流通業者を経由して販売する場合に生じるデメリットは、自社ECという「0段階チャネル」での販売によって、ある程度解消することができます。自社ECに取り組むことで、単にデメリットを解消するだけに留まらず、メリットを生み出す点が重要です。
効果1. 流通マージンを削減できる
自社ECでは流通業者を介さないため、中間マージンはほぼ発生しません。その結果、商品1単位あたりの利益率が向上し、価格政策も柔軟に設定できます。
効果2. 消費者の購買行動や意識を把握できる
購入履歴、閲覧行動、カゴ落ち、レビュー内容など、消費者の購買データや意識に関する詳細な情報を、直接取得でき、マーケティング施策や商品開発に活用しやすくなります。
効果3. 商品を十分に訴求できる
ブランドストーリーや商品の使い方、開発背景など、消費者に伝えたい情報を文字、写真、動画など多様な方法で提供できます。店頭では制約のある情報伝達が、自社ECでは自由に行えます。
効果4. 新商品の販売機会を確保できる
小売店舗で採用されにくい新商品でも、自社ECでは自由に販売できます。まず自社ECで販売し、消費者の支持を得た後に小売店舗での販売を行うという戦略も可能です。
自社ECサイトに取り組む際の4つの注意点
メーカーが自社ECに取り組む際には、いくつか注意しておきたい点があります。特に重要なものには、以下のものがあります。
注意点1. 集客と顧客対応の難しさ
開設したECサイトへの来訪者を増やすためには、広告投資やSNS運用、検索対策(SEO)などのマーケティング施策を計画・実施する必要があります。さらに、既存顧客との関係を維持・強化するCRM施策も欠かせません。また、問い合わせ対応や購入後フォローのための運用体制の構築も求められます。
注意点2. 既存チャネルとのコンフリクト(摩擦)
メーカーが自社ECで販売を強化すると、自社商品を取り扱っている既存小売チャネルと価格や販売施策の面で摩擦が生じる可能性があります。メーカーが消費者に直接販売することは、小売側から見れば競合することになり、扱うメリットが薄れるという懸念にもつながります。価格設定やキャンペーン設計などでバランスを取る必要があります。
注意点3. 物流・発送コストの発生
自社で受注・配送を行う場合、個々の注文に応じたピッキング・梱包・発送作業が発生し、物流コストが積み上がります。冷蔵・冷凍品であれば、温度帯別の配送費用も無視できません。さらに、返品・交換対応、在庫管理や梱包資材の準備など、小売を介さないことで新たに発生する業務負担を見込む必要があります。
注意点4. 自社ECの役割の明確化
単に「ネット上の売場」という位置づけにするのか、「ブランド情報発信」「ロイヤル顧客育成」「高付加価値商品の販売」「定期購入」などの役割を持たせるのかによって、必要な体制や投資は大きく変わります。自社ECの目的が曖昧なままでは、費用対効果が見えづらく、運用が行き詰まりやすくなります。
メーカーが自社ECに取り組む際には、これら4つが特に重要なポイントとなります。
加えて、法規制・品質管理への対応、システム運用コストや決済手数料の負担など、検討すべき項目は多岐にわたります。
食品メーカーの自社EC戦略事例:カゴメ健康直送便
流通業者を介した販売を長年続けてきた食品メーカーが、自社ECサイトを運営するケースは珍しくなくなりました。
以下では、メーカーが自社ECサイトによって「商品を十分に訴求できる」代表的な事例として、カゴメ株式会社の通信販売「健康直送便」を取り上げます。
◆カゴメ健康直送便のトップページ(PC版)
.jpg)
画像出所:カゴメ健康直送便公式サイト(PC版トップページを2025年11月17日に閲覧)
「お店では買えない特別なカゴメ」は少数精鋭
「健康直送便」は、「お店では買えない特別なカゴメ」というコンセプトのもと、通信販売限定の商品をケース販売などで提供しています。取り扱いは少数精鋭で、2025年11月1日現在、販売期間外の商品を含めても約50品目にとどまっています。
カゴメは伝統ある有名ブランドを多数持ち、全国の小売店舗やECモールでも販売していますが、「健康直送便」で扱うのは限定商品です。そのため、消費者に販売する際には商品の説明が欠かせません。扱う品目数が少ないことにより、一品ごとに丁寧な説明を行うことが可能となっています。
「健康直送便」誕生のきっかけと重視していること
「健康直送便」は1998年に誕生しました。そのきっかけとなったのは、夏に収穫したトマトの味や栄養を直接消費者に届ける取り組みとして開発された「夏しぼり」というトマトジュースです。創業百年を控えたカゴメが原点を問い直し、今後の方向性を形にしたこの商品は、大きな反響を呼びました。
◆「健康直送便」誕生のきっかけとなった「夏しぼり」(2025年現在のパッケージ)

画像出所:カゴメ健康直送便公式サイト「夏しぼり(30本)」(閲覧日:2025年10月20日)
当初の想定以上に多く届いた顧客の声は、「健康に役立つジュースを毎日飲みたい」というものでした。
カゴメはこのニーズに応え、さらに期待を上回る喜びを提供するため、「健康直送便」において、野菜や果実を楽しむ飲料、素材を味わう食品、植物由来の成分を凝縮したサプリメントなど、本物にこだわった商品群を展開しました。
また、「健康直送便」では、原料の生産から製造、受注、配送に関わる全ての担当者が、顧客の喜びを励みとしており、消費者とのコミュニケーションを通じて「うれしい」を提供することを重視しています。
情報出所:カゴメ健康直送便公式サイト「カゴメ健康直送便とは」(閲覧日:2025年11月1日)
顧客の支持を集めて好調な「健康直送便」
同社の2025年1~9月の決算によると、通信販売事業では広告費を戦略的に投下した結果、野菜飲料やスープが好調に推移しました。その結果、通信販売事業の売上収益は前年同期比5.0%増の100億76百万円、事業利益は前年同期比20.8%増の7億12百万円となっています。
情報出所:カゴメ株式会社「2025年12月期 第3四半期 決算短信〔IFRS〕(連結)」(公開日:2025年10月29日、閲覧日:2025年11月1日)
電話注文としてスタートした「健康直送便」は、その後、ECモールや自社ECサイトでの販売も展開しています。2025年現在、健康直送便の注文は、ハガキや電話、FAXでも受け付けていますが、売上の大半が自社ECサイト経由のものだと考えられます。
商品の特徴や魅力を丁寧に伝える説明
上述の通り、「健康直送便」で扱っているのは、店舗では販売されていない限定商品です。また、ケース販売など、まとめ買いを対象としています。そのため、顧客に対して、商品の情報を丁寧に伝えることが不可欠です。
「健康直送便」のサイトでは、商品情報をどのように紹介しているのかを見てみましょう。ここでは、代表的な商品である野菜飲料「つぶより野菜」を取り上げます。
◆つぶより野菜

画像出所:カゴメ健康直送便公式サイト「つぶより野菜(30本)」(閲覧日:2025年10月20日)
「つぶより野菜」の商品ページには、上から順に、次の情報が掲載されています。
- 商品画像:複数の画像を順番に切り替えて表示。栄養成分表示も含む
- 商品名:「つぶより野菜(30本)」
- キャッチコピー:「こんなにおいしい野菜ジュースがあったなんて」
- 商品説明(簡易):「野菜本来の味わいを、ぎゅっと閉じ込めて(以下略、約100字)」
- 商品仕様:「内容量 195g/30本/1ケース」
- コース別の価格プラン:定期お届け(3点/2点/1点コース)、1回のみお届け
- 購入ブロック:コース選択と点数選択
- 商品説明(詳細):原材料名、栄養成分表示、賞味期限
- シェアボタン:X、LINE、Facebook、URLコピー
- 別バリエーションのページへのリンク:初回限定セット、小容量タイプへの誘導
- こだわり紹介動画:動画でこだわりを紹介(1分12秒のYouTube動画)
- こだわり紹介文:商品、素材、製法、パッケージ(サイズの大きな文字と写真)
- 商品STORYのページへのリンク:企画担当者が語る商品の秘密への誘導
- おすすめ用途:食事、味付けや隠し味、ギフト、備蓄用
- よくある質問:7つの質問への回答
- クロスセル:同時購買のおすすめ(毎日飲む野菜、野菜と豆の具だくさんポタージュ4種セット)
1つの商品につき、約3,000字をかけて丁寧に情報を伝える構成になっています。文字と写真に加え、商品のこだわりを約1分でまとめた動画も視聴できるため、購入を検討している人が商品に対する理解を深めやすいページです。
◆「つぶより野菜」こだわり動画(画面キャプチャ)
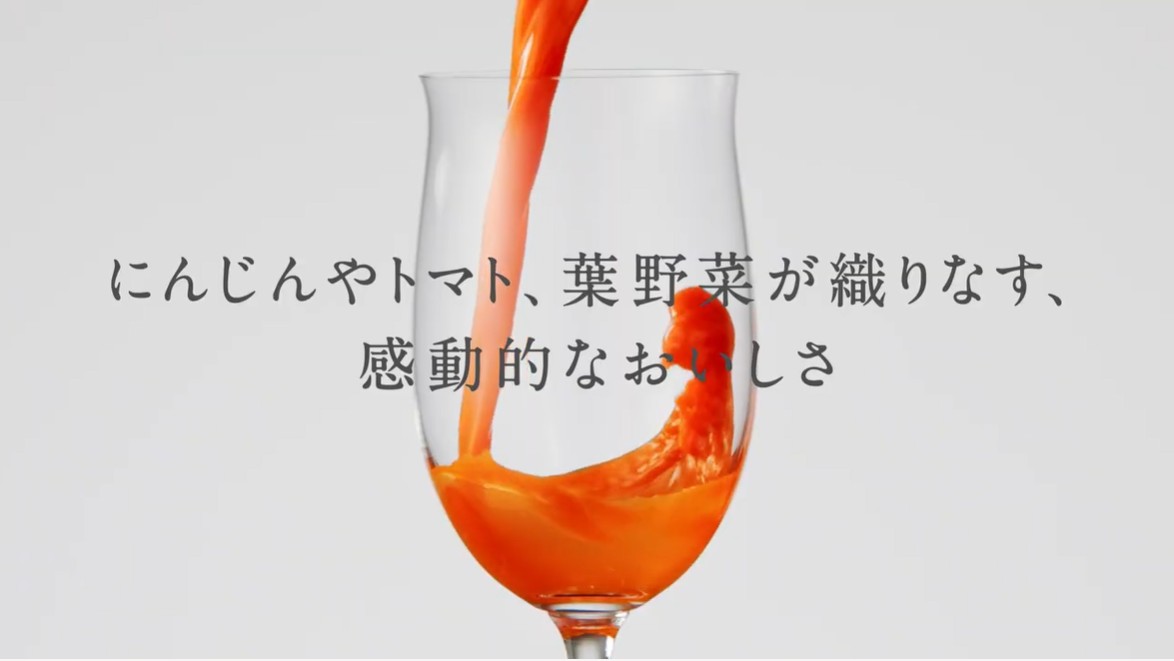
画像出所:カゴメ健康直送便公式サイト「つぶより野菜(30本)」内の動画をキャプチャ(動画公開日:2024年2月20日、閲覧日:2025年10月20日)
また、商品企画担当者が裏話や秘密を紹介するページ「商品STORY」へのリンクも設置されています。
◆商品STORY「つぶより野菜」

画像出所:カゴメ健康直送便公式サイト「商品STORY|つぶより野菜」(閲覧日:2025年11月2日)
各商品の紹介ページとは別に設けられた「商品STORY」のページでは、企画担当者の工夫やこだわり、開発にかける想いなどを紹介しています。
このように、1つの商品について、質・量ともに豊富な情報を伝えられるのが、メーカー自社ECサイトのメリットです。
知ることで好きになる「けんちょくのある暮らし~畑と健康の贈り物~」
「健康直送便」のサイト内には、商品の紹介ページと「商品STORY」の他、「けんちょくのある暮らし~畑と健康の贈り物~」というページもあります(「けんちょく」は「健康直送便」の略)。
このページには、商品に使われている野菜などの生産者を取材して書かれた記事や、素材に対するこだわりを詳細に記載した記事などが、たくさん掲載されています。
◆「けんちょくのある暮らし~畑と健康の贈り物~」

画像出所:カゴメ健康直送便公式サイト「けんちょくのある暮らし~畑と健康の贈り物~」(閲覧日:2025年11月2日)
「けんちょくのある暮らし」に掲載されている記事は、5つのカテゴリーに分かれています。
- 農といっしょに。:野菜や果実の生産者との関わりや品質へのこだわりを紹介する記事
- 野菜といっしょに。:野菜のおいしさと健康を届けるための技術やこだわりを紹介する記事
- けんちょくを楽しむ。:イベントレポートやコラボレーションなど、健康直送便が楽しくなる情報
- けんちょくアレンジ&レシピ:健康直送便の商品をつかったレシピやアレンジ方法などの情報
- みんなの声:日常の中にある「健直のある暮らし」を紹介する記事
このページの想定読者層は、「健康直送便」の既存顧客の中でも、コアなファンが中心だと考えられます。コアなファンに向けて情報を発信できるのも、自社ECサイトを持つことのメリットです。
興味を持ったり好きになったりした対象について、人はより深く知りたくなるものです。そのような顧客が求める情報を継続的に提供することは、ロイヤルティの向上につながります。また、読者からのメッセージを募集し、ページ内で紹介する仕組みも、ファンにとってうれしいものです。
カゴメにおける自社ECサイトの位置づけ
カゴメは、自社ECサイトを単なる「販売チャネル」と考えるだけでなく、顧客とのコミュニケーションの場としても位置づけています。従来の「買ってもらうための場所」という役割に加え、「顧客と語り合う場所」や「カゴメの想いや考えを伝える場」といった役割の比重がむしろ大きくなっているといいます。
また、どこで、誰が、どうやって作ったのか、なぜこの商品が生まれたのか、といった背景情報に価値を置き、生産者や開発者の想いやこだわりを丁寧に伝えることを重視しています。同社は、これにより、顧客が商品を「知って買う」「共感して買う」といった購買体験を得られると考えています。
情報出所:W2株式会社公式サイト「“知る、共感、ファン化、そして購入へ” カゴメが描くコンテンツ起点のEC運営を、W2のシステムで脱・属人化へ」(閲覧日:2025年11月3日)
これらの同社の考えは、先に確認した「健康直送便」のECサイトの特徴に反映されています。顧客は、サイト内で「知る→好きになる・共感する→購入する」という行動を促すようなつくりになっています。まさに、同社の「顧客とのコミュニケーションの場」という考えが、サイトの構造やコンテンツ設計に反映されているといえます。
商品紹介ページでは、文字や写真だけでなく、こだわりを短時間で伝える動画や、開発者・生産者の想いを紹介する文章など、多層的な情報提供が行われています。これにより、顧客は、サイト内で、商品の理解や生産者や開発者への共感を深めながら購買体験を楽しむことができるのです。
まとめ
食品メーカーにとって、自社ECサイトは単なる販売チャネルの補完手段ではなく、消費者との関係を深め、ブランド価値を高める場としての役割を持ちます。従来型のチェーンストアを中心とする小売店の店頭販売には、広範な流通網や販売活動の代行など、多くのメリットがある一方で、顧客の購買行動を直接把握しにくい、伝えたい情報を十分に伝えられない、自社商品の全てを取り扱ってもらえない等のデメリットが存在しました。自社ECは、こうした課題を解消しつつ、メリットを享受できる手段となります。
本稿で自社ECに取り組むことで得られる効果を幾つか挙げました。カゴメの「健康直送便」は、「商品を十分に訴求できる」という効果を得ている好事例です。
商品ページ・商品STORY・生産者取材記事など、多層的な情報提供を通じて、顧客は商品情報に加え、開発の背景を理解し、開発者・生産者の想いに共感した上で購買に至ります。このような購買体験を提供する自社ECサイトは、単なる「買ってもらうための場所」にとどまらず、「顧客と語り合う場所」や「想いや考えを伝える場」の役割を担っており、ロイヤルティ向上にもつながります。
なお、本稿で取り上げたカゴメの取り組みは、メーカーの自社EC戦略の1つの方向性です。今回は取り上げませんでしたが、例えば日清食品グループオンラインストアは「新商品の販売機会を確保できる」という効果を得ている代表事例だと言えます。今後、自社ECに注力しようとしているメーカーにおいては、本稿の「自社ECサイトでの販売によって得られる4つの効果」で解説した内容などを踏まえて、自社が目指す方向を明確にした上で、適切な先行事例から学ぶことが必要です。
本稿の内容が、メーカーなどでECに取り組む方々の参考になれば幸いです。
【宣伝】ブログでECサイトのSEOを成功させる方法とは?
ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。
このメディアを運営する forUSERS株式会社 では、
EC担当者・ライター向けの SEOブログライティング教材 を販売しています。
◆こんなSEOの悩みはありませんか?
✓ ECサイトにSEO対策をしているのにアクセスが伸びない
✓ AIに記事を書かせているが、本当に上位表示できるのか不安
✓ 外注ライターが成果を出してくれない
✓ 自分でSEOブログを書きたいが、何から始めればいいかわからない
そんな方に向けて、
たった 29,800円 で「上位表示を実現するためのSEOブログライティング講座」をご用意しました。
今なら サンプル動画 を無料で視聴できます。
まずは下記リンクから、教材の内容をチェックしてみてください。
◆SEOブログライティング講座




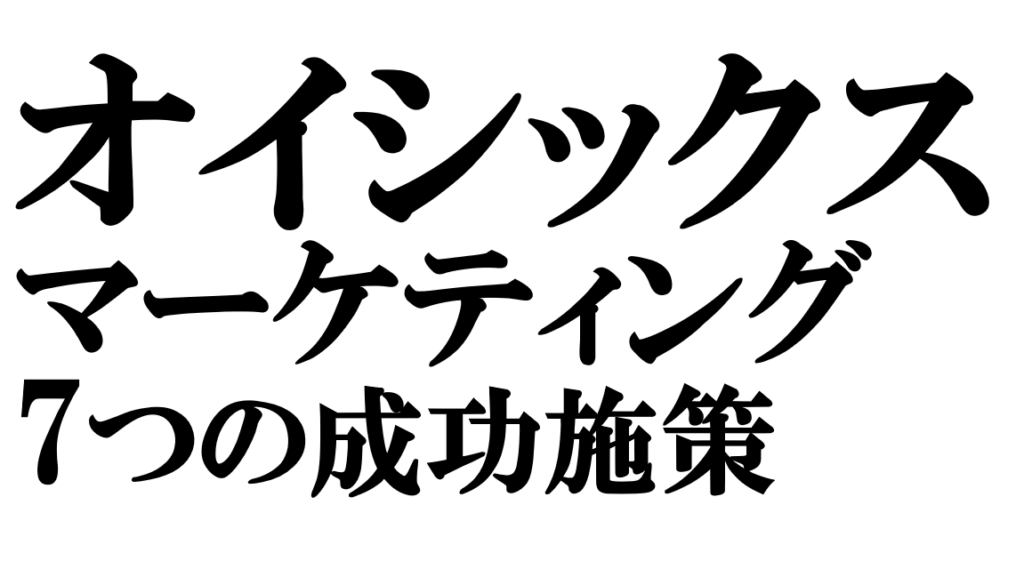
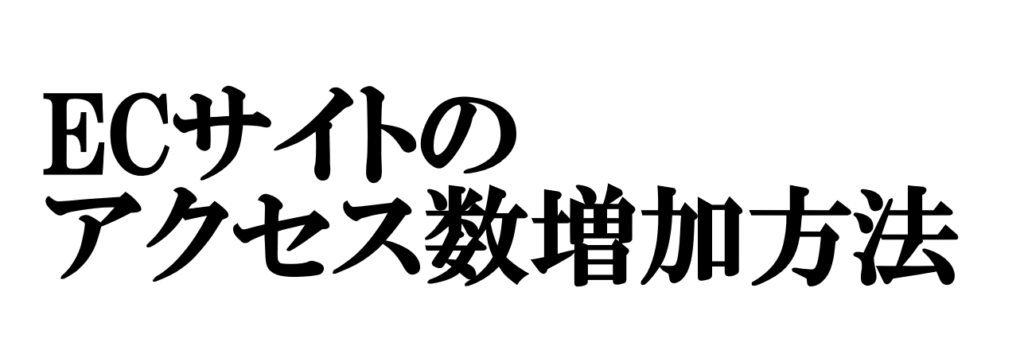
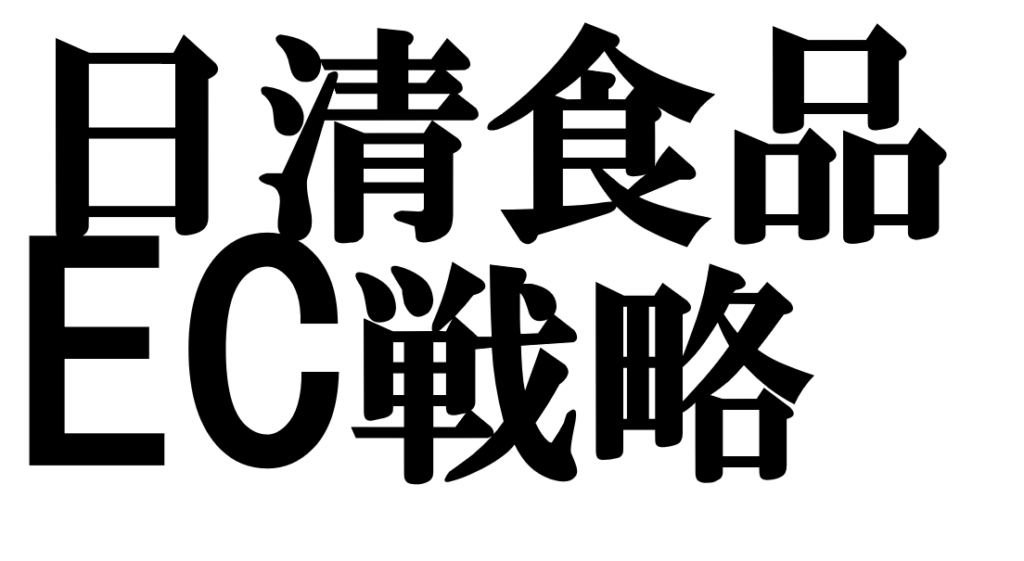
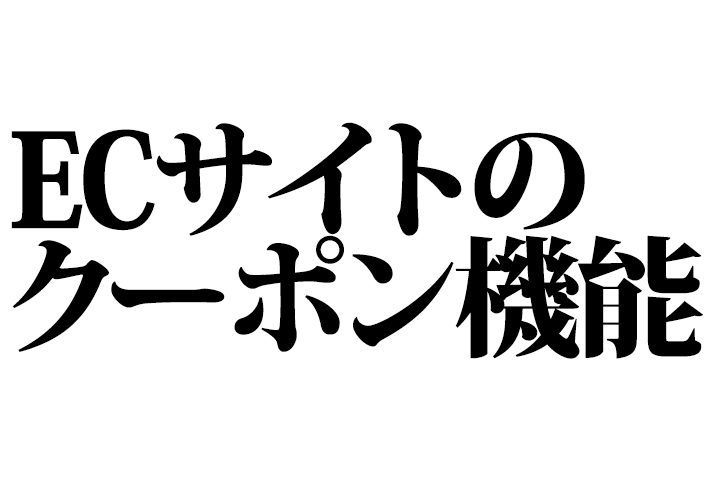

“「食品メーカーのEC戦略」メリット・デメリットとカゴメの取り組み” への3件のフィードバック